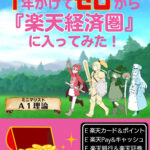2017年8月8日~10日まで、またしても下諏訪に行ってました!!
いつものブログ仲間、このブログの読者の方、ゲストハウス関係の方やゲストの方、下諏訪の地元の方、地域おこし協力隊やその知り合いの方々、等々、、、
3日間、寝ている間以外、温泉の中でさえ、ずっとしゃべりっぱなしでした!w
しかも、なぜか睡眠時間4時間とかで、2日連続朝風呂にも行きましたよ!!w
そのせいか、本日はかなり眠いのですが、下諏訪でいろんなことを、いろんな人と話した過程で、
「地方都市への移住」
について、昨日から少し考えていたので、それをさらに掘り下げてみたいと思った。
でも、疲れすぎてパソコンに向かう気力がなかったので、寝転びながらtwitterで淡々とつぶやいていたので、それを元に記事にしたいと思います!
▼需要もあったので!w
『風の民』『水の民』『地の民』という切り口と考察がとんでもなく面白いです!!
このテーマのブログを読みたいです!! https://t.co/JsjlPhyfra— inspirex@はてなブログ (@inspirex6) 2017年8月11日
うわー、めっちゃ嬉しいです!
楽しみにしてます!!— inspirex@はてなブログ (@inspirex6) 2017年8月11日
というわけで、、、
『下山の時代』
って言う人いるけど、それは完全に資本主義という宗教の範疇の中での発想だと僕は思うな〜。プロダクトの『生産性』がカンストしてるんだから、人類は資本主義の次のフェーズに行くべきで、それ以上でも、それ以下でもないと僕は考える。
ま、多くの人には理解されないけど。 pic.twitter.com/lQK1mLOZXY
— A1理論はミニマリスト (@A1riron) 2017年8月11日
これは▼『成功する里山ビジネス』という本に出てきた一文の中に書いてありました。
でも、この『風の民』『水の民』『地の民』って言葉、僕は聞いたことがなかったし、ググっても出てこない。
でも、
その3種類の人間が存在することは僕の今までの40年間の人生の実感においてはものすごくしっくりきました!!
けど、ひとつ僕は疑問点があって、
「いつの時代でもニューフロンティアはそうやって開拓されてきた。大航海の時代も、アメリカ西部も、ネットビジネスも。」
とあるけど、、、
でもそれは、
「プロダクトの『生産性』」
がカンストするまえの『世界』の話であって、、、
「プロダクトの『生産性』」
がカンストしてしまった21世紀においても果たしてそうなのかな?
僕は、▼こんな風に考える人間でして、、、
人類は『情報革命』により、『資本主義』をも克服しようとしてるんじゃないかな? - A1理論はミニマリスト
『下山の時代』とか『ダウンシフターズ』というのは、基本的に、あくまでも、
『資本主義』という人類最大の宗教
の範疇の中での発想なんじゃないかと考えてしまう人間だ。
僕の考え方はこうだ!
物欲のない僕には、
「カネがあればあんなのも買えるぞ!こんなのも買えるぞ!女にモテるぞ!」
って言われても、なーんにも魅力は感じない(笑)モノはあると邪魔だし、メシは日本食ならそれでいい。
そして、女には昔からモテてたから、特にありがたみを感じない。
むしろコスパ悪い(笑)— A1理論はミニマリスト (@A1riron) 2017年8月11日
ひらやまさん(マスヤードラゴンさん)の車は外車なんだけど、僕にとっては外車もトラックの荷台も、特に機能的には大差ない(笑)
マスヤまで移動出来ればそれでいいのだ(笑)
僕の脳内では『車』以上にアルゴリズム分岐しないし、脳内メモリを消費したくない(笑)
— A1理論はミニマリスト (@A1riron) 2017年8月11日
僕にとっては、外車もトラックも『車』という脳内アルゴリズムの中ではそれ以上分岐しないw
むしろ、車酔いしてしまう僕的には外車よりも車高が高いトラックのほうが格上だったりするw
僕にとってのサイコーの車は『酔わない車』だ!w
で、、、
ま、なにが言いたいのかと言うと『下山の時代』と言う人の考えは多くの人には当てはまるのだろうけど、僕には当てはまらない。
むしろ、20代の時に比べたら、借金もなく、スマホがあり、はてなブログアプリがあり、ゲストハウスがあり、マスヤがある時代は、本当に『豊か』になった時代だと思う。
— A1理論はミニマリスト (@A1riron) 2017年8月11日
つまり、
『足るを知る』
人間にとっては、経済が良くなろうが悪くなろうが、そんなことはたいして重要じゃないのだ。
重要なのは、
「自分と親和性の高い人とつながること」
であって、それに関して一番重要なモノは「ブログ」、2番目に需要なモノは「twitter」、そして3番目に重要なモノは「ゲストハウス」だと僕は思っている。
(で、それらを使うのにおカネはそんなに必要じゃない!)
という僕はレアな『風の民』なんだろうな。
『風の民』が求めているのは、常に『居』場所なんだろうけど、常に『風のモード』なので、一つ所に留まらず、いつもゲストハウスるろうに、みたいな(笑)
『住』居も不要だし、働きたくないでござる!なので、定『職』にも付かない、落ち着きない人。
— A1理論はミニマリスト (@A1riron) 2017年8月11日
『風の民』って、要は▼スナフキンみたいな人間だと僕は思うんですよねぇ。

僕は物心がついたときからたった一人で旅を続けてきた。
多分、これからもそうするだろう。
それが、僕にとっては自然なことなんだ。
それはいいテントだが、人間は、ものに執着せぬようにしなきゃな。
すててしまえよ。小さなパンケーキ焼きの道具も。ぼくたちには、用のなくなった道具だもの
僕のミニマリスト6分類で言えば、
『家さえも断捨離』系ミニマリスト
▼とも言える。
ミニマリストを『家』別に5タイプに分類してみたよ!それぞれのタイプの愛読書も紹介!(追記で計6タイプになりました) - A1理論はミニマリスト
ハンタで言うと▼『ジン・フリークス』が一番近いと僕は思う。
最新刊発売!HUNTER✖︎HUNTER33巻のジン・フリークスの言動が、僕の「理想のミニマリスト」過ぎた! - A1理論はミニマリスト
天下を取ってまでバックパッカーになろうとした▼黒田官兵衛のように、永久に「自分と親和性の高い人間」を探し続けている人種なんじゃないかな?
天下最も多きは人なり、最も少なきも人なり。(黒田如水) - A1理論はミニマリスト
ま、▼『モバイルボヘミアン』ですな!w
逆に長野移住相談に来るような人は『水の民』なんだろうな。
移動可能なんだけど、『風の民』よりは、もう少し落ち着きたいし、妻子も持ちたい、みたいな。
すでに実績のある定『職』を持ってるので、やっぱりこの人達が欲してるのも『居』場所なんだろうな。
ただし、物理的な『居』場所だ。
— A1理論はミニマリスト (@A1riron) 2017年8月11日
で、それより少しマシ定住志向なのが『水の民』なんだろうな。
気に入った町に工房を作ったり、オーガニックなカフェを開いたり。
今日読んだこの人も▼『水の民』なんだと思う。
働かず、遊ぶ日が多いほど、仕事のパフォーマンスは上がる!成長とともに自分の客単価は上げていっていい!DQN客・DQN取引先は断捨離!! / “休みが多いからこそ、鮨屋として、いい仕事ができるんです。 | カンパネラ” https://t.co/Ov6CLJM2Cf
— A1理論はミニマリスト (@A1riron) 2017年8月10日
都会にも住めるし、田舎にも住める人。
『風の民』のような、るろうに、風来坊、フーテンではなく、まぁ、ちゃんとした社会人ではある。
しかし、『風の民』ほどではないにしろ、
『水の民』も絶対数はかなり少ない
と僕は思うなぁ。
今の自治体の『地方移住』は、この数少ない『水の民』の牌(パイ)を取り合っているようにも思える。
で、最後の、、、
『地の民』が欲してるのは、単純に『職』業という仕事なんだろうな。
ただ、こういう人って、移住したがるのか?って思う。
都会より家賃は下がるけど、給料も下がるし、実家住まいならさらにコスパ悪くなる。
そんな土着の方々が移住するようになるのかは僕は疑問だ。『居』場所はすでにあるし。— A1理論はミニマリスト (@A1riron) 2017年8月11日
『地の民』は大多数のホワイトカラーやブルーカラーのことを指すと思う。
20世紀はこの『地の民』の消費によって経済が回ってきたようにも思える。
いわゆる▼『ヤンキー経済』。
若者が物を買わなくなったとされている現代においても、物を旺盛に買っているとされている層というのがヤンキーであり、このようなヤンキーの消費動向を述べた書籍。この書籍で述べられているヤンキーというのは現代においてのヤンキーということであり、昔のように暴れまわっていたヤンキーとは異なったマイルドなヤンキーということである。この書籍によればヤンキーというのは今後の経済を担う層とのことであり、このことからこの書籍から今後の日本人の消費動向が分かるとのことである。
レアな『風の民』は、
そもそもモノを買わない。
なぜなら、移動生活においては、なにかとかさばるモノの時点で邪魔だからだ。
必要なモノはその都度、100円ショップで買うか、ゲストハウスで貸してもらえばいい。
つまり、生涯バックパッカー。
『水の民』にとって、モノは「少数精鋭」が基本で、必要以上のモノは買わないんじゃないかな?
『中道ミニマリスト』という感じで、自分が持つモノにはこだわる。
しかし、人口の大多数を占めるであろう『地の民』は、相変わらず、20世紀型、アメリカ型の『大量生産大量消費社会』に生きているんじゃないかな?
休日はイオンモールの往復で終わる、的な。
で、
20世紀はそんな『地の民』を集めることが『経済を回すこと』だったように思える。
なので、20世紀では『水の民』、ましてや『風の民』なんて、変わり者でしかなかったし、経済に貢献しているとは思われてなかった。
しかし、
『水の民』は少数精鋭でこだわりの好きなモノを集める。
たとえば、オーガニックカフェの店主が、店内の内装やモノにこだわったり、工房の店主が豆にこだわった珈琲を淹れてくれたり。
いうなれば、
『少量生産少量消費』
であって、全体のおカネの流通量には『地の民』と変わりがない気がする。
で、問題は、モノ自体に興味がない『風の民』だけど、、、
『風の民』は『居』場所を求めながらも落ち着かず常に旅を続けるのは、求めてる『居』場所が、物理的な居場所ではなく、仮想的な居場所なんだろうな。
彼らは、スマホ、ブログ、twitter、facebook、note、VARU、polca等のサービスが出るのをずっと待ってたんだろうな。
— A1理論はミニマリスト (@A1riron) 2017年8月11日
『風の民』が人生において最重要視しているのは『居』場所だ。
しかも、それは『物理的な居場所』ではなく、『仮想的な居場所』だ。
そんな『風の民』は、
「こいつらは経済を回してない!!」
と、いつの時代も批判の槍玉にあげられてきたけど、
今は『情報革命』により、ブログも含めた自分の『作品』をクラウド上に置いておくことにより、クラウドファンディング、note、VARU、polca等でおカネを集められるようになってきたし、そのおカネでまた旅をし、その旅をまたクラウド上にブログ等でアップすることで、さらに資金が集まる!!
という社会になってきた。
『ニートの歩き方』のphaさんも、
「ネットの恵みで生きる」
と言っている。
これらすべては『情報革命』の恩恵であり、人類進化の最適解であると僕は考える。
なので、今は『風の民』『水の民』『地の民』、それぞれで経済が回っていて、ひとつの町単位で経済を回す時代ではなくなってきてるんじゃないかな?
下諏訪で言えば、
線路の南が『地の民』で経済が回っているエリア、
線路の北が『水の民』で経済が回っているエリア、
そしてマスヤゲストハウス内部のマスヤバーが『風の民』で経済が回っているエリア、
と言えるんじゃないかな?
なので、、、、
移住者誘致って、最終的には『地の民』を呼び込みたいんだろうけど、これって、要件定義以前に、企画定義が破綻してねーか?(笑)
って、よく思う。田舎にいっぱい仕事があれば別だろうけど、日本は東京だけがズバ抜けて最強の超サイヤ人孫悟空で、あとはヤムチャとか餃子レベルだと思う(笑)
— A1理論はミニマリスト (@A1riron) 2017年8月11日
『地の民』で移住に興味があるのは、ホワイトカラーで、かつPCに詳しくて、地方にも興味がある人くらいなんじゃないかな?
「テレワーク」に反応するのはほんの一部の人達だけだと僕は思う。
まとめると、
『風の民』が求めてるのは仮想的な居場所なので、彼らは定住はしないスナフキン。
『水の民』が求めてるのは物理的な居場所なのでゲストハウスの近くに工房とかオーガニックカフェを作ったりするけど、そもそもそれが出来る人の絶対数ってそんなに多いのかな?
— A1理論はミニマリスト (@A1riron) 2017年8月11日
『地の民』が求めてるのは、単純に割りのいい仕事。
でも、それだけなら日本には東京という最強都市があるから、東京周辺で安い家を見つけた方がいい。娯楽もあるし。
もしくは生まれ育った地元の子供会小中高のコミュニティという居場所が居心地過ぎて移住なんて考え方しないだろう。
— A1理論はミニマリスト (@A1riron) 2017年8月11日
そう考えると、この『風の民』『水の民』『地の民』が無理に混じり合わず、住み分けされるほうが人類にとっては幸せなようにも思える。
すでにアメリカではブルックリンやポートランドはそうなってるし、日本でもそうなるんじゃないかな?
だって日本の『地の民』はアメリカ以上に動かないから。
— A1理論はミニマリスト (@A1riron) 2017年8月11日
なので、
『風の民』『水の民』『地の民』を無理に混ぜ合わせないほうがいいんじゃないかな?
彼ら3民族は共通言語を有してないw
それこそ、同じ町内で▼『文明の衝突』が発生するw
いわゆる「ハレーション」ってヤツだ!

- 作者: サミュエル・P.ハンチントン,Samuel P. Huntington,鈴木主税
- 出版社/メーカー: 集英社
- 発売日: 1998/06/26
- メディア: 単行本
- 購入: 17人 クリック: 915回
- この商品を含むブログ (87件) を見る
21世紀に大事なのは、
『文明の衝突』を起こさずに、それぞれの民族の中メインで経済を回すこと
なんじゃないかな???
星川さんも、
「バンドマンの中で経済を回そう!」
って▼いつも書いている。
売れないバンドマンだってお金持ちにならなければダメだ - 俺、まちがってねぇよな?
「バンドの客はバンドマン」ってバカにされることがあるけど、それで全然良い。
むしろセカンドクリエイター時代の今はその方が良い。問題はバンドマンがお金もってないからそこで経済が回らないことだと思う!
と、まぁ、いろいろ考えてみたけど、正直、よくわからない(笑)
ただ、ひとつだけわかるのは、俺が働きたくないってことだけだ!!(笑)
— A1理論はミニマリスト (@A1riron) 2017年8月11日
と、よくわからなくなったところで、整骨院にでも行くか(笑)
— A1理論はミニマリスト (@A1riron) 2017年8月11日
ただ、
じゃあその3民族の間に『ベルリンの壁』を作ればいいのか?
というと、
僕はそうは思わない。
3民族の分類はあくまで属性であって、その中に好みもあるし、考え方の違いもあるし、僕の言葉で言うと『A1能力』の違いもある。
僕的には、
「民族が違っても、交流したい人はゲストハウスのバーとか交流スペースとかで交流すべき!」
と思っている。
姫姉様のように、
ゲストハウスに住み込みで働いた感想と生活費! - 時間セレブ
ゲストハウスのヘルパーをやって良かったと思うことは人とコミュニケーションを取ることがお仕事だという点です。他人に興味津々な私にとっては天国です!!
ゲストハウスにいるだけで色んな地域から色んな人が来るので愉快です!
「他人に興味津々な人」
というのは民族を問わずにいると僕は思う。
『風の民』な旅人でも、ゲストハウスで交流しまくる松鳥むうさんのような人もいれば、ドミで1人静かに本を読んでいる人もいる。
『水の民』の移住者でも、工房で黙々と作業するのが好きな人もいれば、お客さんと2時間くらいしゃべり続ける人もいる。
『地の民』でも、小中高のコミュニティから出ない人も多いけど、新しい出会いを常に探し続ける人もいる。
つまり、
「他人に興味津々な人」
は各民族にいて、それを結び付けているのがゲストハウスのバーや交流スペース、もしくはイベントだと僕は思っている。
その最大の町が僕的には下諏訪で、僕は、大げさに聞こえるかもしれないけど、
下諏訪は壮大な人類の実験場
だとも思っている。
旅人をマスヤから動けなくする『マスヤトラップ』を仕掛け続けるモストデンジャラスコンビ!!(笑) / “【マスヤヘルパー】~その21~肩を組む親子。 - 僕は僕らしく生きて行く自由があるんだ” https://t.co/y1EPcvpT42
— A1理論はミニマリスト (@A1riron) 2017年8月11日
というわけで、まとめると、
『風の民』『水の民』『地の民』は無理に交わると『文明の衝突』というハレーションを起こす
しかし、
各民族のうち「他人に興味津々な人」はいると思うので、そんな人たちは交流するべきで、そのためにはゲストハウスのバーや交流スペースが一番、効率的だよ!
ってことで!
で、そういう「他人に興味津々な人」って、
「頭がいい人」
というより、
「頭が柔らかい人」
なんだろうな、たぶん。
そして、僕は、
『他人を認めあえる社会』こそが、一番『豊かな社会』だ!
と考えるミニマリストです!w
というわけで、最後にもう一度、『風の民』であるスナフキンの言葉でお別れしたいと思います!
人と違った考えを持つことは一向にかまわないさ。
でも、その考えを無理やり他の人に押し付けてはいけないなあ。
その人にはその人なりの考えがあるからね
追記:
『地の民』は、
労働はオフライン
成果物の販売もオフライン『水の民』は、
労働はオフライン
成果物の販売はオンライン『風の民』は、
労働もオンライン
成果物の販売もオンライン— A1理論はミニマリスト (@A1riron) 2017年8月11日